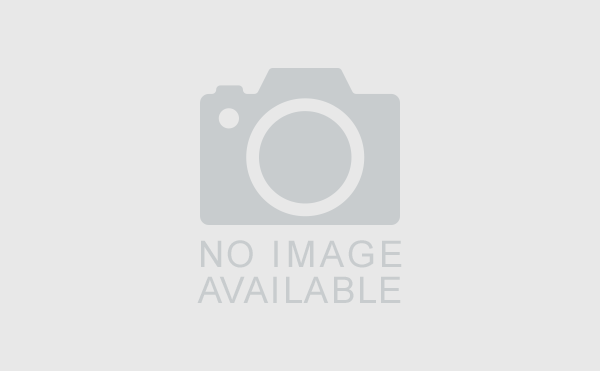バセドウ病に対する放射性ヨウ素内用療法についての安心で心強い研究結果
バセドウ病に対する放射性ヨウ素内用療法後に甲状腺がんの発症頻度が増えるかどうかについては、今までに賛否両論がありました。2022年にこの論争には決着が付いたように感じて、甲状腺ニュースでも公開しました(バセドウ病に対するアイソトープ治療とがんの関連性について)。しかし、バセドウ病に対する放射性ヨウ素内用療法後の甲状腺がん発症については、まだ完全決着はついておらず、くすぶった状態のようです。つい最近、日本からこの問題について医師、患者にとって安心できる貴重な報告が、米国内分泌学会から出版されている臨床内分泌代謝雑誌(JCEM)に掲載されました(Occurrence of Newly Diagnosed Thyroid Cancer Is Not Increased After Radioactive Iodine Therapy for Graves' Disease. JCEM AOP 2025 )。今回は、このことについてお話したいと思います。
結論を先に述べますと、「バセドウ病に対する放射性ヨウ素療法後、新規甲状腺がんの発症率は増加しない」です。甲状腺専門病院として有名な東京の伊藤病院からの報告です。
2007年1月から2016年12月までの10年間に受診した未治療バセドウ病は15175名で、バセドウ病と診断された時点で甲状腺がんと診断された93名と6ヶ月以内に他院に転院もしくは受診しなくなった患者1208名の合計1301名を除外した13874名を対象として、最長16年間経過をみて、新規に甲状腺がんと診断された症例について比較検討しています。13874名の内訳は、放射性ヨウ素内用療法2273名、抗甲状腺薬治療11314名、手術287名です。甲状腺がんの頻度は、放射性ヨウ素内用療法0.35%(8名/2273名)、抗甲状腺薬治療0.34%(39名/11314名)、手術0.00%(0名/287名)でした。すなわち、各治療法間で、新規の甲状腺がん発症頻度には差はみられませんでした。
放射線被ばくから放射線誘発性甲状腺がんの発症には一定期間を要すると考えられていますので、観察期間が5年以上、10年以上の症例のみを対象としたが、放射性ヨウ素内用療法と抗甲状腺薬治療の間では甲状腺がんの頻度に差はありませんでした。また、詳細な検討を行ったが、甲状腺がんを発症した症例とそうでない症例では甲状腺がん発症の危険因子に差は認められませんでした。さらに、甲状腺がんはほとんどが微小甲状腺がんであり予後不良を示す証拠は見つかりませんでした。
この報告は、医師、患者にとってバセドウ病に対する放射性ヨウ素内用療法を行うまたは受ける上で重要かつ貴重な情報になると信じます。
文責:田尻淳一